|
|
上越市大豆から見た春日山城
|
|
|
|
|
宝物館、春日山神社近くにある謙信の銅像
|
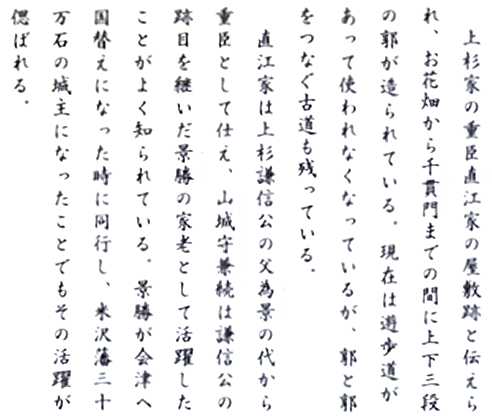 |
直
江
山
城
守
屋
敷
跡
|
|
|
|
|
|
|
直江屋敷へ上る途中から見た本丸
|
|
直江山城守(兼続)宅址 |
| 毘 沙 門 堂 |
| このお堂には謙信公の信仰された毘沙門天の尊像(青銅製、約50cmが安置されています。尊像は景勝公のとき会 |
| 津を経て米沢に移りましたが、嘉永2年の火災で痛みました。昭和3年に第15代上杉憲章氏が東京美術学校に修理を |
| 依頼され、名匠高村光雲先生が1年余を費やして修理いたしました。 |
| そのさい先生は御分身をつくり、尊像の欠け損じたのをおなかに入れて同5年3月に完成し、当市(当時春日村)に |
| 寄進されました。 |
| 毘沙門天は悪魔を降す神です。謙信公は自らの軍を降魔の軍とみなし、毘の字の旗を軍頭にかざし、また事あるとき |
| はこの堂前で諸将に誓いを立てさせました。毘沙門天は四天王のうち、北方を守る多聞天でもありました。 |
| この尊像は多聞天のお姿です。公は王城の北方を守る意気をもっていたものとおもわれます。 |
|
|
|
|
|
|
| 左: |
直江宅から上る道。左上:本丸、右少し上:毘沙門堂
|
| 右: |
毘沙門堂。謙信が信仰した毘沙門天の尊象(青銅製、約50cm)が安置されています。
この毘沙門堂の向かって左側に『不識院址』の古い石碑があるので、
以前の史跡定説と現在の史跡定説に違いがあるのかと思えます。 |
|
|
|
|
|
地図では、護摩堂、諏訪堂になっていますが、
古い石碑は『毘沙門堂』となっています。 |
|
|
本丸横(高さは本丸とほぼ同じ)の天守台址 |
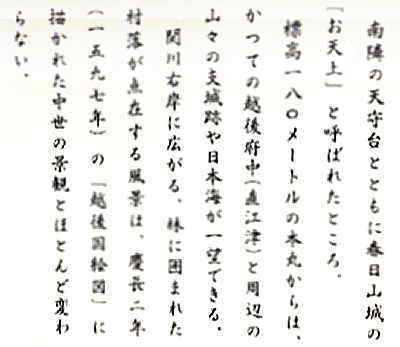 |
本
丸
|
|
|
|
|
|
|
天守台と並ぶ本丸
|
|
本丸にある謙信作の歌 |
|
|
本丸からの眺め。3km先の日本海が見えます。
|
|
|
本丸からの眺め
|
|
|
|
|
今も水を湛える大井戸(天守台と本丸の間の道を下った西側にあります。)
|
|
|
|
|
油流し
本丸の西斜面は急傾斜でまるで油を流したよう!
|
|
大井戸からの道
左の階段:鐘楼へ 右下の道:景勝屋敷へ |
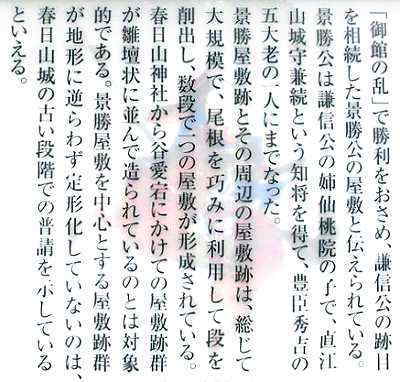 |
上
杉
景
勝
屋
敷
跡
|
|
|
|
|
|
|
かなり広い景勝屋敷址
撮影者の背後一段低い所に柿崎屋敷址があります。 |
|
|
| 柿崎和泉守屋敷跡 |
| 上杉謙信の重臣柿崎影家の屋敷跡と伝えられる春日山城で最も大きな郭の一つです。 |
| また、城内の山地で唯一ハンノキが自生する場所で、植性から水分を多量に含む土地で |
| あったことがわかります。ここに堀、もしくは水堀があったことが考えられます。 |
| 池であったとすれば、春日山城で唯一庭園を合せもった郭の景観が想像されます。 |
| 屋敷へは、木橋をかけた南側の空掘を渡って入るように古絵図に描かれています。また、 |
| 郭の東側を通り、景勝屋敷に登る古道も残っています。 |
|
|
|
|
|
|
とても広い柿崎和泉守宅址
撮影者の背後一段高い所に景勝屋敷址があります。 |
|
|
景勝屋敷と柿崎屋敷を直接結ぶ道 |
| 桑取道(春日山古道) |
| 春日山5か年整備事業計画の一環として、柿崎屋敷から牛池・城ヶ峰・ |
| を経て中桑取に至る古道(桑取道)を整備しました。謙信公の時代は、 |
| 春日山城と北陸方面を結ぶ重要な軍道だったと言われています。途中 |
| の城ヶ峰は、標高295メートル、春日山城の砦で越中(富山県)方面 |
| の見張りを果たしたとも伝えられています。 |
| 柿崎屋敷4km→牛池新田3.6km→城ヶ峰2km→高住バス停 |
|
|
|
|
|
| 柿崎屋敷から桑取道が繋がっています。 |
|
桑取に繋がる道
|
| 二の丸 |
| 本丸から毘沙門堂を経てお花畑に至る実城と呼ばれる郭群の東裾を取り巻く |
| ように造られた郭で、実城とともに春日山城の中心地区をなしています。本丸の直下 |
| にあって、本丸を帯状に囲っている様子は、まさに本丸の警護として造作されたこと |
| を示すものと考えられます。 |
| 古絵図には、「御2階」「台所」と記されたものもあり、現在も笹井戸といわれる井戸 |
| 跡も残っていることも、当時の二の丸における生活を知る手掛かりになっています。 |
|
|
|
|
|
|
| 左: |
本丸東側直下にある二の丸(帯郭) |
| 右: |
二の丸にある笹井戸。
ここには、井戸(笹井戸)があり、
古い絵図によると
「お茶屋」「台所屋敷」「人数溜」「お二階」「二段目」
などがあったところです。
この井戸は新しい案内板の後ろにあり、左の画像では影になり見えません。 |
|
|
|
|
|
| 左: |
山裾から二の丸直下まで延びる縦堀の一部。
自然の地形に手が加えられています。
この頁の一番下に、下から見た縦堀の画像があります。 |
| 右: |
土塁
ここには、当時の土塁が残っており、この上に城壁があり、
鉄砲を撃つときの銃眼や弓を射る場所に使われました。 |
|
 |
上
杉
三
郎
景
虎
屋
敷
跡 |
|
|
|
|
|
|
| 上杉景虎屋敷址 |
|
景虎屋敷址の向いにある米蔵址 |
上杉景虎屋敷と米蔵を総称して三の丸と呼びました。
御館の乱のとき、景虎は米蔵の米を持って出たのでしょう。
兵糧攻めに出来ると考えたのではないでしょうか。 |
|
|
|
|
|
| 左: |
三の丸から更に下ったところにある甘糟近江守宅址
甘糟近江守は、永禄4年の川中島合戦で勇猛果敢に戦いました。
|
| 右: |
二の丸まで続く縦堀
縦堀に向かって左に景虎屋敷、右に直江屋敷があります。
私は、縦堀に向かって右側(直江屋敷側)から上り、左側(景虎屋敷側)から下りました。 |
|
|
|
|
|
|
|
城内には桜が咲いていました。(ピンボケですが・・・。)
雪の中にカタクリも咲いていましたが、
写真を撮るのを忘れました。 |
|